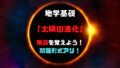受験科目にもある地学基礎!
満点が狙える科目と言われており受験で使うならぜひ押さえておきたい科目です!
その地学基礎の宇宙分野の「太陽系」についての用語を一緒に確認していきましょう。
・地学基礎を受験で使う予定
・地学基礎の「宇宙分野」の用語を覚えたい!
・太陽系のことを詳しく知りたい!
※最後に問題形式の用語リストもあるのでみてみてください。
地学基礎の宇宙分野は大きく分けると次の3つ
- 太陽の特徴について
- 太陽系について
- 太陽の進化について
- 銀河系と宇宙の構造について
その中でも今回は「太陽系」についての用語のみを紹介します!
「太陽の特徴」については下の記事をみてみてください!

「太陽の進化」については下の記事をみてみてください!

地学基礎「太陽系」について
太陽系とは私たちが住んでいる地球を含めた惑星と太陽さらに小天体を含めたものを言います。聞いたことはあると思いますが意外と知らないことは多いですよね。
「太陽系」についていくつかの分野に分けたので早速覚えていきましょう!
太陽系を構成する天体
太陽系を構成する天体
恒星:太陽(恒星とは自ら光輝く星のこと)
惑星:太陽から近い順に
水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星
(覚え方:すいきんちかもくどってんかい)
小天体:小惑星、太陽系外縁天体(冥王星など)、彗星、衛星
太陽系でよく使う距離の単位
天文単位(AU):1天文単位(1AU)≒ 1.5億km
1天文単位は地球から太陽までの平均距離です。
太陽~海王星までの距離 ≒ 30天文単位
太陽系の大きさ:1万天文単位以上
太陽系の歴史
太陽系の誕生は今から46億年前とされています。
宇宙空間に漂っていたガスや塵が互いの重力によって引き寄せあい太陽系が誕生したとされています。
ガスの主成分は水素(H)とHe(ヘリウム)です。
太陽系の形成モデル
原始太陽の形成
星間物質が自身の重力で集まり収縮することで原始太陽が誕生しました。
【原子太陽系星雲】
原始太陽が誕生した際に残りの星間物質は太陽を中心に回転運動をしながら円盤状に分布します。それが原子太陽系星雲です。
微惑星の形成
星間物質のうち大きめの塵が衝突・合体を繰り返して微惑星が誕生しました。
微惑星の直径は1~10km
成分は太陽に近い領域と遠い領域で異なり
太陽に近い領域:主に岩石と金属
太陽から遠い領域:岩石と金属と氷
原始惑星に成長
微惑星が衝突と合体を繰り返すことで原始惑星に成長します。
もとになる材料が多かったため太陽から遠い領域でできた原始惑星は大きく成長したと考えられています。
惑星について
地球型惑星
太陽に近い領域にある惑星の事で具体的には以下の4つ
水星、金星、地球、火星
地殻やマントルが岩石で、中心部の核は金属(主に鉄)でできている
サイズは小さめ
※岩石惑星とも呼ばれています。
地球がこれに当たるのでイメージしやすいでしょうか。
木星型惑星
太陽から遠い領域にある惑星のことで具体的には以下の4つ
木星、土星、天王星、海王星
表面は厚いガスに覆われていて、表面下は液体の金属水素、中心部の核は岩石か氷でできている
サイズは大きめ
※巨大ガス惑星とも呼ばれています。
地球型惑星と木星型惑星の比較
大きさ:地球型 < 木星型
密度:地球型 > 木星型
| 地球型惑星 | 木星型惑星 | |
| 名前 | 水星、金星、地球、火星 | 木星、土星、天王星、海王星 |
| 半径 | 小さい | 大きい |
| 質量 | 軽い | 重い |
| 密度 | 大きい | 小さい |
| 自転周期 | ゆっくり | 速い |
| リング | なし | あり |
| 衛星数 | ないor少ない | 多い |
各惑星の特徴
水星
地球型惑星:主に岩石や金属
太陽系の惑星の中で最も半径が小さく、質量も小さい。
表面には無数のクレーターが存在する。
水星には大気がないので隕石が表面まで到達しやすいためと、水もないのでクレーターが侵食されずに残るためです。
自転周期が長い(約58日15時間)
大気が存在しないため昼間は暑く(約700K=約400℃以上)、夜は寒い(約100K=-180℃以下)
↓水星について詳しくはこちら↓
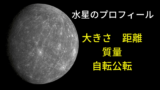
金星
地球型惑星:主に岩石や金属
地球とほぼ同じ大きさ
自転と公転の向きが逆でありこれは金星のみ
厚い大気をもち(90気圧)成分は主にCO2
それによって温室効果があるので表面の温度は約730K=460℃
↓金星について詳しくはこちら↓
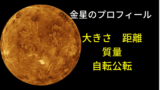
地球
地球型惑星:主に岩石や金属
太陽系で唯一液体の水が存在する。
ハビタブルゾーン内を公転している。
H2Oが液体の水として存在でき、生命が存在するのに適した領域
ハビタブルゾーンは太陽からの距離(公転半径)が重要となっており、太陽系では地球のみがハビタブルゾーン内にある。
例えば、水星や金星は太陽に近すぎてH2Oは水蒸気(気体)になってしまい、火星では太陽から遠いのでH2Oは氷(固体)になってしまう。
月はハビタブルゾーン内にある天体だが天体のサイズが小さいので質量も小さい
そのため大気や水を表面に留めておくだけの重力が足りない。
火星
地球型惑星:主に岩石や金属
半径は地球の半分程度で自転軸は地球のように傾いている。
大気の主成分は:CO2
大気圧:地球の1/100以下
河川の跡のようなものがあるため、かつては液体の水が存在していたとされる(現在は発見されていない)
↓火星について詳しくはこちら↓
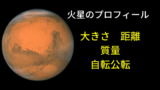
木星
木星型惑星:主にHとHeから成るガスからなる惑星
太陽系で最大の惑星。
表面には大赤斑(だいせきはん)と呼ばれる大きな渦がある。
表面温度は-150℃
衛星が60個以上もある。
↓木星について詳しくはこちら↓
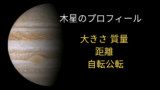
土星
木星型惑星:主にHとHeから成るガスからなる惑星
太陽系で2番目に大きな惑星。
平均密度は太陽系で最小。
望遠鏡で観察できるリング(環(わ))を持つ。
幅は約7万kmですが厚さは最大数百mほどとかなり薄い。
主な成分は氷で岩片などが多数集まったものでできている。
木星と同じく衛星は60個以上もある。
↓土星について詳しくはこちら↓
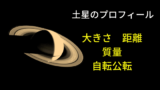
天王星・海王星
木星型惑星:主にHとHeから成るガスからなる惑星
天王星と海王星は大きさ・構造ともに似ている。
表面温度もともに約-200℃以下。
天王星の特徴は公転面に対して自転軸が横倒しになっている点です。
その他の小天体
衛星
惑星のまわりを公転している天体のこと。
上にも書きましたが木星型惑星は多くの衛星をもっています。
衛星として有名なものはもちろん月ですよね。
月の特徴は以下の通りです。
半径は地球の約1/4、表面は岩石。
白く見える部分:クレーターが多く高地
黒く見える部分:クレーターが少なく平坦な部分(海)
木星型惑星は衛星を多数もっています。
【代表的な衛星】
木星の衛星「イオ」では火山活動が確認されており、
土星の衛星「エウロパ」では液体の海が存在するとされています。
小惑星
主に火星と木星の間を公転している岩石からなる小天体のこと
50万個以上発見されていて、それらが小惑星帯を形成しています。
多くの小惑星は直径10km以下ですが、中には直径1000kmの小惑星「ケレス」も発見されています。
日本でもニュースとして大きく取り上げられた日本の探査機「はやぶさ2」が調査した「リュウグウ」も小惑星の1つです。
太陽系外縁天体
海王星の外側を公転している小天体のこと
氷を主体とする小天体です。
冥王星は2006年までは惑星に分類されていましたが、冥王星に似た大きさの天体が発見されはじめ「準惑星」という新しい分類をつくり冥王星がその分類になりました。
今では冥王星よりも大きな太陽系外縁天体も発見されています。
彗星
太陽の周りを楕円・放物線・双曲線軌道をとる天体のこと
彗星の本体は核と呼ばれる直径数kmほどの天体で、氷を主成分としてその他にも塵や岩石も含まれています。太陽に近づくと太陽から放射される熱でガスや塵を放出させます。これは「コマ」と呼ばれていて明るい部分です。
この時放出されたガスや塵は太陽の影響(太陽風)によって太陽と反対側に伸びる「尾」を発生させます。
尾には
ガスがイオン化して輝く「イオンの尾」(青)と
塵が日光を反射して輝く「塵の尾」(白)の2種類あります。
隕石
小惑星帯にある小惑星の断片が剥がれ落ち、地球など他の天体に接近し衝突したもの
大きな隕石の衝突の跡には円形のクレーターが形成されます。
「太陽系」について問題形式
太陽系の恒星は太陽のみ
(覚え方:すいきんちかもくどってんかい)
1天文単位 ≒ 1.5億km
太陽系の大きさ:1万天文単位以上
星間物質のうち大きめの塵が衝突・合体を繰り返してできたのも
太陽から遠い領域:岩石と金属と氷
木星型惑星:木星、土星、天王星、海王星
中心部の核は金属(主に鉄)
サイズは小さめ
表面下は液体の金属水素
中心部の核は岩石か氷
サイズは大きめ
木星型惑星:巨大ガス惑星
密度:地球型>木星型
衛星数:地球型(少ないor0)<木星型(多い)
自転周期:長い(約58日15時間)
大気がないので隕石が途中で燃え尽きず表面まで到達しやすく、
水がないので浸食されずにクレーターが残っているため
夜は寒い(約100K=-180℃以下)
成分は主にCO2
表面温度は約730K=460℃(温室効果があるため暑い)
主成分:CO2
衛星数:60個以上(多い)
幅:約7万km
厚さ:最大数百m
主成分:氷と岩片
表面の成分:岩石
黒く見える部分:クレーターが少なく、平坦(海)
※月の直径3,474km
現在の分類は太陽系外縁天体(準惑星)
塵の尾:成分は塵、塵が日光を反射して輝く、色は白
天体の大気で燃え尽き表面に達しないものは隕石ではない
問題は以上になります!
これを覚えれば地学基礎「太陽系」についての語句問題はできますよ!
次回は地学基礎「太陽の進化」について紹介します!
↓「太陽の進化」について↓

↓「太陽の特徴」について↓