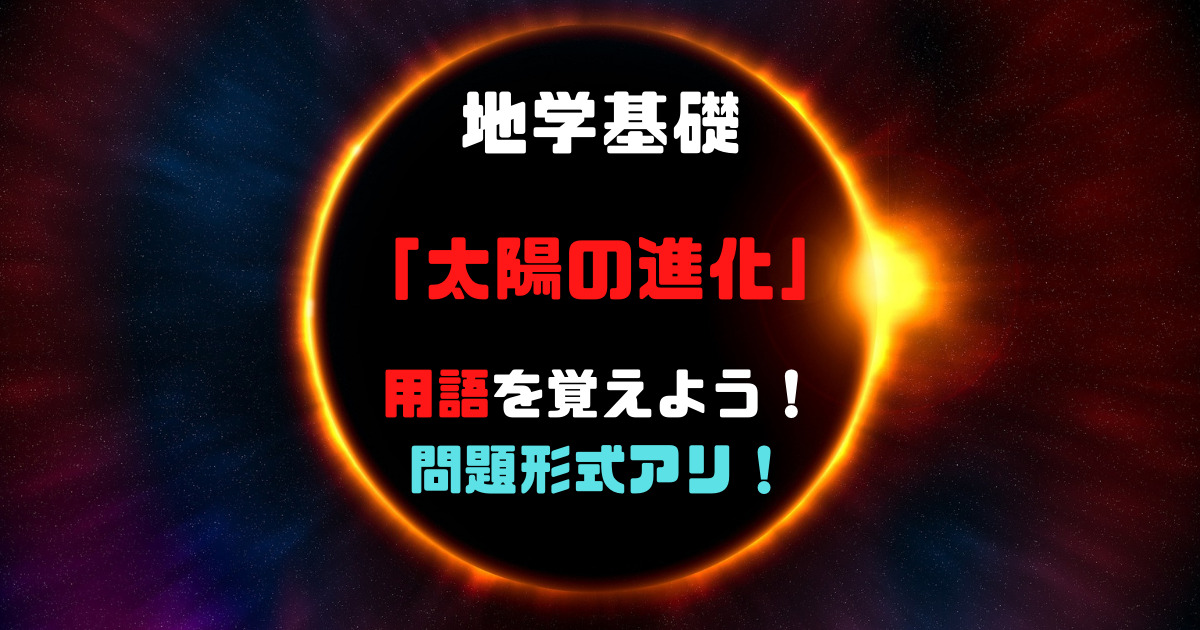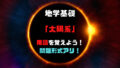受験科目にもある地学基礎!
満点が狙える科目と言われており受験で使うならぜひ押さえておきたい科目です!
その地学基礎の宇宙分野の「太陽系」についての用語を一緒に確認していきましょう。
・地学基礎を受験で使う予定
・地学基礎の「宇宙分野」の用語を覚えたい!
・太陽の進化のことを詳しく知りたい!
※最後に問題形式の用語リストもあるのでみてみてください。
地学基礎の宇宙分野は大きく分けると次の3つ
- 太陽の特徴について
- 太陽系について
- 太陽の進化について
- 銀河系と宇宙の構造について
その中でも今回は「太陽の進化」についての用語のみを紹介します!
「太陽の特徴」については下の記事をみてみてください!

「太陽系」については下の記事をみてみてください!

地学基礎「太陽の進化」について
等級
※「等級」は入試本番でも計算問題として頻繁に出題されます。
夜空に見える星はほとんど全てが恒星です。(恒星とは自ら光り輝く星のこと)太陽系では太陽が唯一の恒星ですね。
そんな恒星の明るさのめやすとして等級という単位が使われています。
等級は1等級、2等級と数えるのですが数が小さいほど明るいと定義されています。
ちなみに基準は0等級の「こと座のベガ」です。
恒星の明るさのめやすの単位
数が小さいほど明るい
1等級と2等級の明るさの違いはどれほどなのでしょうか?
それは次のように定義されています。
5等級小さくなると明るさは100倍になる
では1等級違うと20倍違うのでしょうか?
実は違います。
5等級で100倍なので1等級だと\(\sqrt[5]{100}\) ≒ 2.51倍ほど明るさが異なります。
(2.51を5回掛けると約100になる)
中でもよく使われるのが見かけの等級と呼ばれるものです。
これは地球からみたときの星の等級のことです。
地球からみたときの等級
「最初に説明した等級となにが違うの?」って思いましたか?
微妙に違います。
下の表をみてください。
| 恒星の名称 | 見かけの等級 |
| 太陽 | ー27 |
| シリウス(おおいぬ座) | ー1.4 |
| ベガ(こと座) | 0 |
| ベテルギウス(オリオン座) | 0.42 |
| デネブ(はくちょう座) | 1.25 |
| アルタイル(わし座) | 0.76 |
これを見ると太陽が特別に明るい恒星のように思いませんか?
答えは「NO」です。
太陽は地球からの距離が近いので明るく見えますが、他の恒星は地球から距離がとてつもなく遠いので等級も最大で-1.4程度になってしまうのです。
先ほどの表にいくつか列を追加しましょう。
| 恒星の名称 | 見かけの等級 | 地球からの距離(光年) | 絶対等級 |
| 太陽 | ー27 | 0.000 016 | 4.8 |
| シリウス | ー1.4 | 8.60 | 1.4 |
| ベガ | 0 | 25.03 | 0.6 |
| ベテルギウス | 0.42 | 642 | ー5.4 |
| デネブ | 1.25 | 1411 | ー6.9 |
| アルタイル | 0.76 | 16.7 | 2.2 |
※絶対等級とは恒星を地球から一定の距離に置いたときの明るさ
つまり絶対等級をみることで恒星自体が放つ明るさがわかります。
等級の問題
太陽と月(満月)の明るさは何倍違うか?
ただし太陽の等級を-27、月(満月)の等級を-13とする。
-27-(-13)=-14
つまり太陽の方が14等級明るい
————————
5等級差=100倍(覚える)
1等級差=約2.5倍(覚える)
————————
10等級差⇒100×100=10000倍=1×104倍
15等級差⇒100×100×100=1×106倍
14等級差⇒1×106÷2.5=4×104倍
つまり
答え:4×104倍
太陽の誕生と進化
太陽の誕生
太陽のつまり恒星の誕生を説明するにはまず下の用語を説明しないといけません。
用語を覚えて下さい!
星間物質
星間物質とは星間ガスと固体微粒子のことをいいます。
星間ガス:恒星と恒星の間に存在する水素、ヘリウム
固体微粒子:直径0.01~1μm(マイクロメートル)の塵
※1μmは1mmの千分の一
星間雲(せいかんうん)
宇宙の中で星間物質がほかの領域よりも濃く集まっている領域のこと
【星間雲の種類】
散光星雲(さんこうせいうん)
星間雲のなかでも近くの明るい星の光を反射して輝いて見えるもの
暗黒星雲(あんこくせいうん)
地球との間にある星間雲によって背後の星の光がさえぎられ黒く見えるもの
↓星雲の種類について詳しくは↓

原始星
星間雲のなかでも特に密度の高い部分が自身の重力によって収縮することがあります。
収縮すると何が起こるのか?
それは中心の密度・温度が高くなり恒星が誕生します。
それを原始星といい、原始星の段階の太陽を原始太陽といいます。
また、原始太陽の期間は約300万年続いたとされています。
現在の太陽
主系列星
原始星がさらに自身の重力で収縮し、中心部の温度が約1000万K以上に上昇すると、中心部で水素(H)がヘリウム(He)に変わる核融合反応が起こります。
この核融合反応の核エネルギーで恒星は輝くようになります。
つまり原始星はまだ輝いていない星だったんですね。
この核エネルギーは恒星を膨張させるというはたらきもあります。
すると恒星自身の収縮させる力(重力)と核エネルギーの膨張させる力がつりあって収縮は止まります。
この段階の恒星を主系列星といい、恒星は最も長い期間この主系列星という状態にあります。
ちなみに現在の太陽はこの主系列星です。
太陽の寿命
現在の太陽は主系列星の状態はずっと続くのでしょうか?
答えは「NO」です。
太陽の場合だと主系列星の期間は約100億年と考えられており、現在の太陽は約46億歳なので残りはあと54億年(50~60億年)とされています。
逆に言えばあと50~60億年は太陽は現在のまま輝き続けるということです。
核融合反応では水素がヘリウムに変化しています。
つまり太陽では水素がどんどん減っているのです。
将来の太陽・太陽の最後
核融合反応が進むととなにが起こるのでしょうか?
太陽の中心部では水素が減り、ヘリウムが増えます。
水素は核融合反応の燃料です。その水素が減り続けるといつかは核融合反応が起こらなくなります。
さて、主系列星では「収縮させる力(重力)と核エネルギーの膨張させる力がつりあっていたので太陽の大きさは安定している」と説明しました。
しかし核融合反応が起こらなくなると膨張の力がなくなるので中心部は自身の重力で収縮します。
では太陽はどんどん小さくなっていってしまうのでしょうか?
答えは・・・そう「NO」です。
赤色巨星
中心で核融合反応が起こらなくなると中心部の外側で水素の核融合反応が起こるようになるのです。
つまり中心部の外側はまた膨張の力がはたらくので恒星が急激に膨張するのです。
その膨張した恒星を赤色巨星といいます。
赤色巨星は主系列星に比べ半径も明るさも大きな星です。
表面温度は約6000Kから3000Kに下がり、明るさは約1000倍になると考えられています。
赤色巨星になったあとの中心部はどうなるでしょうか?
中心部は自身の重力で収縮しているので温度が上がります。
温度がどんどん上がり約1億Kに達するとヘリウムが核融合反応を起こします。
ヘリウムの核融合反応でできる原子は炭素や酸素です。
この期間は膨張していた星も収縮に転じるのですが、ヘリウムも使い切って中心部が炭素や酸素の核になると再び膨張を始めるのです。
どんどん膨張すると太陽はどこまで大きくなるのでしょうか?
それは太陽は現在の約200倍にまで膨張すると考えられています。
どのくらいかというと水星はもちろん金星の軌道を超え地球のすぐ近くまで太陽がくるということです。
惑星状星雲→白色矮星
中心部でヘリウムがなくなると核融合反応は止まってしまいます。
赤色巨星はとても大きいので中心から遠い部分では重力の束縛から逃れることができるので外側のガスが流れ出します。
それによってできるのが惑星状星雲と呼ばれているものです。
↓星雲の種類について詳しくは↓

さらに時間が経つとガスも失われ、中心部には白色矮星(はくしょくわいせい)と呼ばれる天体が残ります。
白色矮星は比較的高温また高密度で、大きさは太陽の1/100程度です。
白色矮星は核融合反応が停止しており徐々に暗くなっていく恒星の最後の姿です。
星間雲
↓
原始星
↓
主系列星
↓
赤色巨星(せきしょくきょせい)
↓
惑星状星雲
↓
白色矮星(白色矮星)
↓星の一生について詳しくは↓
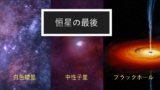
「太陽の進化」問題形式
※0やマイナスの値もある
1等級小さいと約2.5倍明るい
星間ガス:恒星と恒星の間に存在する水素、ヘリウム
固体微粒子:直径0.01~1μm(マイクロメートル)の塵
暗黒星雲:地球との間にある星間雲によって背後の星の光がさえぎられ黒く見える星間雲
↓
中心の密度・温度が高くなり恒星(原始星)が誕生
(水素の核融合反応)
恒星自身の重力による力(収縮)がつりあって収縮は止まる
その段階の恒星を主系列星という。
※現在は約46億歳
⇒恒星が急激に膨張する。
その状態の恒星を赤色巨星という。
明るさ:1000倍
温度が1億Kになるとヘリウムの核融合反応が起こる。
⇒再度膨張を始める
⇒太陽の大きさが水星はもちろん金星の軌道を超え地球のすぐ近くまで
密度:高密度
大きさ:太陽の1/100程度
問題は以上になります!
これを覚えれば地学基礎「太陽の進化」についての語句問題はできますよ!
次回は地学基礎「銀河系と宇宙の構造」について紹介します!
↓「太陽の特徴」について↓

↓「太陽系」について↓